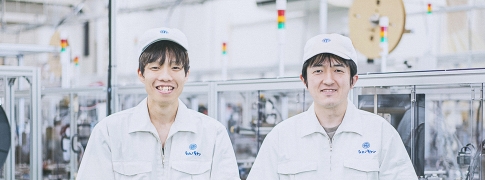技術者インタビュー 02_技術一課
ひとつの金型に
微細加工40工程を凝縮
インタビューされる人
- 技術一課課長
- 高 道TAKAMICHI
| 2002年入社
大学では機械システム工学を専攻。機械の魅力は、力の方向や量を変換をするといったしくみにあると言う。趣味は庭いじりで、8年ものの盆栽を育てている。
インタビューする人
- 技術一課
- 田 村TAMURA
| 2017年入社
機械システム工学科を卒業後、将来性の高い電子部品分野を志望して当社に入社。休日は大学時代に作ったチームでサッカーを楽しむアクティブ男子。
これまでで
最も印象深い仕事とは?
- 田村
- 高道課長はずっと金型設計だったんですか?
- 高道
- 入社して1年くらいプレス加工をして、その後はずっと技術1課(プレス金型の設計・製作部門)。
- 田村
- そうだったんですね。今までで一番大変だった仕事って何ですか?
- 高道
- んー、10年目の頃に参加した、金型の「構造改革プロジェクト」かな。
- 田村
- どういうプロジェクトなんですか?
- 高道
- 標準化されてるプレス金型のプレートの厚みや、位置決めをするポスト、加工する製品の高さ設定なんかを見直して、低コスト化・高速化につなげようというプロジェクト。金型を軽くすることを目標にしたんだけど、結論から言うと、半年くらい毎日やって完結に至らなかったんだよね。
- 田村
- え、できなかったんですか?
- 高道
- うん。その頃は標準化されている仕様を真似て設計していただけで、金型の構造をちゃんと理解できていなかったと思う。完成はしなかったけど、非常に勉強になったという意味で印象に残っています。
- 田村
- どこがうまくいかなかったんですか?
- 高道
- 単純にプレートを薄くすると、中のバネが弱くなって製品が振動してしまうとか、水平垂直がズレやすくなるとか、別の問題が発生するんです。それまでは金型部品の精度ばかりを重視していたけれど、標準化の意義や、穴やポストの位置が精度につながるということを改めて理解しました。
- 田村
- そういう勉強の機会があったというのは、むしろ羨ましいですね。

金型設計・製作は、
どこが面白いと思いますか?
- 高道
- 田村には今、主に試作をしてもらってるけど、仕事はどうですか。
- 田村
- 大変なところもありますが、求められる製品ができ上がった時にはやりがいを感じます。狙い通りに曲がらなかったら作り直しですし、プレスする材料でも変わるので一筋縄ではいかないですけど。
- 高道
- 田村は、非常に気を使って試作をしてくれてるなと思ってます。細かいところによく気づいて、不具合を見逃さないところとか。
- 田村
- ありがとうございます。後工程で不良になる方が大変なので…。
- 高道
- 金型は、どれだけ部品の精度が良くても、組み込みが悪かったら良い製品ができない。それではどこに問題があるか判断しにくくなるから、今後も組み込みを大事にして試作にトライしてください。
- 田村
- はい。課長は、この仕事のどういうところが面白いと思いますか?
- 高道
- 自分で考えて調整しながら、うまく製品ができた時はやっぱり面白い。そこは同じです。
- 田村
- ひとつの金型で何十工程もこなすっていうのは、会社見学をした時に初めて知ったんです。
- 高道
- 金型の部品は多いもので600、大きいもので1mもあります。薄い平材を型抜きして、送って、曲げて製品に仕上げるまで、多ければ40工程をひとつの金型内でやるわけだから、加工工程が多いほど金型が難しくなるのは確かだよね。
- 田村
- 分からない時は先輩に相談できるので悩み込むようなことはないですけどね。一旦自分で考えてみて、聞く時は現状と課題を伝えるようにはしています。

若手のうちに
大事にすべき
ことは何でしょうか?
- 高道
- そういう、自分で考えてやってみるという経験をいっぱいしてもらいたいなと思います。もちろん私もいっぱい先輩方に教えてもらったんだけど、経験上、自分で考えたことの方がより自分の財産になると実感しているので。
- 田村
- わかりました。今はまず、試作の仕事をもっと早くできるようになりたいですね。で、いつか0から100まで全部自分でできるようになれればと思っています。
- 高道
- 若手には、ある日突然設計をお願いすることになると思うので、その時のために「自分だったらこう設計したい」という思いを大事にしていてほしい。製品の難易度はどんどん高まっているので、それに対応できる技術を持っておくために、私自身も頑張っていきます。



自分で考える余白と
相談しやすさのバランスが良い環境。
この職場は私にとって、話しやすい人の多い、雰囲気の良い環境です。自分で考えるためのある程度の自由度を保ってくれながらも、必要な時は気兼ねなく相談できる、ほどよい距離感がひとつの魅力だと感じています。学生時代は仕事に慣れるのに時間がかかるのではと不安もありましたが、1年目はインストラクター制度もあって、心配は無用でした。